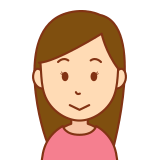
認知症の方の対応に苦手意識がある。適切なケアのポイントがあったら教えてほしい。

苦手意識を持つ気持ちはとてもよくわかります。今回はアルツハイマー型認知症の方に対する適切なケアのポイントについてまとめていきます。少しでも参考になれば幸いです。
アルツハイマー型認知症の中核症状と周辺症状、それらの病期について
まずは問題となる中核症状と周辺症状について確認します。中核症状とは脳細胞が壊れることによって直接的に起こる症状で、要は主症状或いは本質的な症状と言えます。記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下等がそれに当たります。
一方、周辺症状とは中核症状である認知機能障害を背景にして生じる不安や混乱をベースに、周囲との関わりのなかで生じる症状を意味しており、一般的には行動・心理症状(BPSD)と呼ばれています。それぞれの症状は密接に関わっているため、問題解決のためには切り離して考えないように気を付けましょう。各症状は下記の通りです。
| 中核症状 | 記憶障害、見当識障害、思考・判断・遂行機能障害、注意障害、失行・失認・失語 |
| 周辺症状(BPSD) | 精神症状:不安、焦燥、妄想、幻覚、抑うつ 行動障害:徘徊、多動、不潔行為、収集癖、暴言暴力、介護への抵抗 |
病期はHDS-RやMMSE等のテストで評価したり、実際の生活状況や介護状況から判断することになります。下記の表にはHDS-Rの点数に応じたそれぞれの症状を大まかに示しています。すべてがこの通りではなく症状がオーバーラップして現れたり、ほとんど現れなかったりします。参考までに。
| 初期(HDS-R 18-25) 中期(HDS-R 8-18) 末期(HDS-R 0-8) 終末期 | |
| 記憶障害 | 近時記憶障害 即時記憶障害 遠隔記憶障害 完全健忘 |
| 見当識障害 | 時間の失見当 場所の失見当 人物の失見当 |
| 言語障害 | 健忘失語 感覚性失語 全失語 |
| 精神症状 | 不安、うつ、妄想(幻覚・せん妄) |
| 行動障害 | 多動、徘徊、暴力 |
| 運動障害 | パーキンソン症状 失禁 寝たきり 痙攣発作 ミオクローヌス 四肢拘縮 |
中核症状:記憶障害
アルツハイマー型認知症は陳述記憶、すなわち新たな出来事を記銘することが困難になります。一方手続き記憶、すなわち自転車に乗ったり古い道具の使ったりといった体で覚えたこと、体験談等は障害されにくい傾向です。以下、記憶障害のケアについてまとめてみます。
過ぎたことは言わない
数分前の出来事も覚えていないので「さっきは○○でしたね」といった話しかけはかえって混乱を招き、不安になったり、相手が自分に嘘を言っていると思って興奮させてしまうといった結果を招きます。
声かけを頻回にする
コミュニケーションが多いほど記憶に残ります。例えば食後に「朝から何も食べていない」等と訴える場合も、声かけがなく一人で食べているときに生じやすいです。
刺激のある生活を援助する
自分から行動することが難しくなりADLや認知機能の低下につながるため、認知症高齢者が昔やっていたことや興味・関心を示すことを探り刺激のある生活を援助します。
記憶への援助
カレンダーに日々の予定や出来事を書き込むと数日前の出来事を再認できたり、予定を忘れずに実行できたり不安感を和らげることができます。声かけには季節感のある話題にする等、見当識に関する情報をさりげなく多く含めるのも良いでしょう。メモリーノートを用意して本人が覚えておきたいことを日ごろから書き留めるようにするのも良い手段と言えます。
固執への対応(同じ質問や行動を繰り返す場合)
冷静に忍耐力をもって対応する
同じ言動を繰り返しても否定や説得はせず、その都度初めて聞いたように受け答えします。対応される方はかなりの忍耐力を要して大変ですが、やはりこれが堅実な方法と言えます。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どんなふうに)を質問して、何に最も不安を感じているのかを把握します。雰囲気を変えるためにさりげなく話題を変えたり、興味や関心のあることをしてもらうのも良いでしょう。このような行動の背景には不安感が隠れていることが多いため、安心感を与えることが不可欠です。
一時的に離れる
人がいること自体が刺激になる可能性もああります。良くも悪くも忘れてしまうため、物理的に離れて一旦仕切り直すのも良いでしょう。
進行した記憶障害への対応(過去の生き生きとした時代に暮らしている場合)
過去に生きていることを受容する
認知症が進行すると過去に生き生きとした頃のエピソードのなかで暮らすようになります。今の状態が認知できず、自分の居場所がない等の不安から生じ、現実からの逃避とも考えられます。無理に現実に戻そうとせず、まずは本人の話を傾聴して受容するようにしましょう。
今の状況を心地良いものにする
受容したうえで本人の関心あることや出来ることを見つけてあげると過去にいる時間が減少していきます。
中核症状:見当識障害
見当識障害は初期認知症の診断に有用な指標で、「時間」「場所」「人物」の順番に見当識障害が出現します。特に「人物」の見当識障害のなかでも、自分が何者であるかという自己見当識を失うことが不安に陥れます。適切なケアやリハビリで自己を再認識できると不安を背景にした症状は軽減します。
認知症高齢者は記憶障害に基づいて見当識障害が現れます。そして場所や時間の見当識から現在の状況判断ができず強い不安に包まれ、この不安が妄想や徘徊といった周辺症状の基盤となります。このような不安を取り除くことがケア全般の基本となります。
受容と共感的な態度
認知症が進行して異食・奇声等の行為が見られるようになっても、まずは受容することが求められます。受容することによって相手に安心感をもたらします。
馴染みの関係性を築く
不安な混乱を取り除くには馴染みのある関係を作ることが有効です。本人の生活歴を配慮した環境作り(例えば昔使っていた道具や慣れ親しんだものを部屋に用意する等)を行いましょう。
穏やかな刺激のある生活を支援する
他人との接触は脳の刺激にとても有効(楽しめることが前提)であり、他人の役に立つ喜びを味わうことも重要です。刺激のない生活は廃用につながるため、自分でできることは自分でするという姿勢の援助、いわゆる自立支援が必要となります。さらに生きがいとなるような楽しみや役割を見つけ、日々の生活に取り組むことが大切です。
5W1Hの質問とパターン分析により真のニーズを把握する
周辺症状は「何かがおかしい」という合図であり、満たされないニーズを表現しています。真のニーズを把握して周辺症状を把握するには、5W1Hの質問をすることで何に不安を感じているのかを知る手段となります。また言葉で答えられないような状態の方でも、周辺症状の前後にどのような行動をとるのかを観察しましょう。例えば尿意・便意・疲れ・不安・苦痛等があるときのシグナルはどのようなものかを知っておくことで、「イライラの原因は便意かもしれない」といった気づきに結びつくことも多々あります。
笑顔を誘う
楽しい会話をしてくれる介護者には心を許しやすく馴染みの関係にもなりやすいです。笑顔は心を安定させ健康な生活を送るには欠かせません。
心地よい生活空間の工夫
在宅ならば部屋はできるだけ居間の近くにして、声かけがしやすく個室に閉じこもらないようにします。施設では同じ介護者や利用者と馴染みの関係ができやすい環境になるよう、居間やホールに自分の居場所となるような空間が用意されていることが望まれます。認知症高齢者は環境や状況の変化に対処することが困難となっているため、新築の家や施設の居室は見知らぬ世界でしかありません。使い慣れた家具を基の部屋の配置のまま置くことも混乱を避ける方法です。
周辺症状(BPSD):妄想
妄想の内容は被害妄想が主であり、中でも物盗られ妄想が7割くらいと言われています。妄想は記憶障害といった中核症状を基盤に発症しますが、発症の直接的な誘因は認知症高齢者の置かれている状況や周囲との対人関係にあります。したがって記憶障害だけでは妄想は発症しません。例えばこれまで家庭内のことを仕切ってきた人が、認知症を患って自分がケアされる側に回るというように対人関係に変化が生じると、そのことが不安と葛藤を生みだし、妄想を作り出してしまいます。
認知症高齢者は「無くした」と自己嫌悪の方向に考えるのではなく「盗られた」と責任転嫁の方向に考えてしまう傾向にあります。これには自身の記憶障害を認めないアルツハイマー型認知症の病識欠如が基盤となっていることが多いです。ちなみに余談ですが物盗られ妄想は女性に多く発症すると言われています。
幻覚・妄想への対応
実際には生じていない事象が、本人にとっては現実に体験している事実となっているのが幻覚・妄想です。したがってこれを否定しても無意味であり。否定は強化につながってしまいます。対応としては受容的な態度をとり、否定も肯定もしないことが大切です。介護者はその場に応じた「よき演出者」となり、妄想に触れないようヒラリとかわしていくのがコツです。
幻視・幻聴への対応(亡くなったはずの夫が手招きして呼んでいる場合)
幻視・幻聴があるときは本人も不安を感じている場合が多いです。まずは5W1Hの質問をして本人が見えているもの、感じているものを把握してその世界を受容します。不安材料がわかったら否定せず受容し、その不安を取り除くために、例えば「ご主人はすぐこちらに来られるようですから、お茶でも飲んで待っていましょう」といった具合で実際にお茶を飲むようにします。これもまた「よき演出者」となって対処していきます。
物盗られ妄想への対応(お金と通帳を取られたという場合)
まずは否定せずに話を聞いて受容し、5W1Hの質問で真のニーズを把握します。それでも見つからないことを不安がるようであれば「一緒に探しましょう」と対応します。実際に探してみて、本人に見つけてもらうようにうまく誘導して一緒に喜びます。少し間を置いて他に興味があることに誘って一緒に過ごすことも良いでしょう。また普段から介護者が保管しておいて必要に応じて差し出すのも良いでしょう。物盗られ妄想は不安や寂しさから生じる場合が多いため、手提げ復路に入れて常時身近に持っておくことも場合によっては良さそうです。
周辺症状(BPSD):徘徊
徘徊には➀徘徊ではない徘徊、➁反応性の徘徊、➂せん妄による徘徊、➃脳因性の徘徊、⑤「帰る」「行く」に基づく徘徊に分類されます。まずは一つずつ見ていきましょう。
➀徘徊ではない徘徊
場所の見当識障害のため外出すると道がわからず迷子になっている状態。
➁反応性の徘徊
馴染みのない場所に置かれることによって生じる見当識障害と不安を基盤にして出現する徘徊。どこにいるのかわからない、家に帰れないという不安から歩き回る徘徊。新しい環境に慣れて「頭の中の地図」ができれば消失するが時間を要する。
➂せん妄による徘徊
夜間に発生することが多く(夜間せん妄)、せん妄状態にあるので集中力や注意力がなくボーっとして視線が定まらない。夢遊病のように突然ふらふらと歩きだす傾向。
➃脳因性の徘徊
脳の器質的障害による衝動性亢進の症状の一部。歩行ルートはいつも同じような軌跡を描き、速足で硬い表情、前に人が立っていても押しのけるように歩くのが特徴。常同行動の類に近い。
⑤「帰る」「行く」に基づく徘徊
不安な現在から生き生きとした過去の時代への帰郷願望。例えば女性なら「家に帰ってご飯の準備をしなければ」とか、男性なら「職場へ行く」等と訴えること。徘徊というよりは無断外出に近く、特に夕暮れ時に多いため「夕暮れ症候群」とも呼ばれている。
徘徊のケア
徘徊は一般的に場所の見当識障害と不安を基盤としています。したがって対応の基本は不安を軽減することで、「場所を覚え、環境に慣れ親しみ、今いる場所が楽しいところとなり、他にどこにも行く必要がないと思えるようになること」が重要です。部屋に昔使っていた道具やお気に入りのものを置いたり、笑顔で対応して明るく居心地の良い雰囲気を作ることも大切です。これを踏まえたうえで、先ほどの➁~⑤の徘徊のケアについて考えていきます。
➁反応性の徘徊
早めに慣れて安心して暮らせるよう、ポイントとなる場所がすぐにわかるようにします。例えばトイレには大きく「便所」と書いて提示します。不安感や孤独感を和らげるために、馴染みの関係ができるよう辛抱強く援助します。
➂せん妄による徘徊
せん妄の原因を特定して治療するのが第一です。強引に押さえつけたりすると興奮して乱暴になることがあるため注意が必要です。昼夜逆転による夜間不眠でもせん妄が起こるため、日中はしっかりと覚醒して夜間はしっかりと眠れることが大切です。
➃脳因性の徘徊
まだ活力があり他のことに関心が強い状態なので、運動や散歩といった活動的な興味を引くことに注意を向けるのがポイントとなります。
⑤「帰る」「行く」に基づく徘徊
現状の生活に満足感がないからと考え、本人の興味を引くものを探し、楽しむ屋仕事を提供します。
周辺症状(BPSD):うつ
アルツハイマー型認知症では40~50%にうつ症状が出現します。特に発症初期では身体の衰えや記憶力低下から喪失感を持ちやすく、加えて記憶障害や失見当識から自分の置かれた状況が正しく認識できず強い不安を持っています。うつ症状に対してはとにかく不安にさせない、或いは不安を取り除くケアが基本となります。
周辺症状(BPSD:せん妄
単純な意識障害ではなく、意識混濁に幻覚や興奮状態といった精神症状を伴っています。会話が混乱して場所や時間、人物の見当識障害といった軽度の意識障害の症状に加え、幻視や錯視が出現して妄想につながることもあります。引き出しから物を出したり入れたりといった無意味な反復行為もよく見られます。
アルツハイマー型認知症そのものだけで出現することは稀で、骨折・入院・拘束・不適切な薬物投与・ストレス等が誘因となって出現することが多いです。転居をきっかけにストレスと不安をかかえ、せん妄を発症することもあります。
せん妄は急激に発症し症状が変動するのが特徴です。一方、アルツハイマー型認知症は徐々に発症・進行するのが特徴でせん妄のように強い変動はありません。したがって症状が急激に変動したり急速に進行する場合は、アルツハイマー型認知症を患っていたとしても、まずはせん妄を疑うことが重要となります。
せん妄状態への対応としては、決して怒らずに笑顔でじっくりと話を聞く受容的な態度で接すると次第に興奮が落ち着いてきます。
その他の周辺症状:不潔行為
不潔行為とは排泄物を弄んだり尿をまき散らすことを言います。それぞれの行為には様々な原因があるため、その原因を取り除いたりうまく対処することで不潔行為が軽減することがわかっています。中等度の認知症では羞恥心が残っていることが多いため、対応によっては悪化させてしまう場合もあります。できれば叱ったりせず、汚染物を処理するときは小言や文句を言わずに淡々と作業することが大切です。
残便・残尿・便秘による不快感
残便・残尿・便秘の場合、その不快感から手で便を取り出そうとして汚してしまうことがあります。水分摂取を促したり、食事の工夫や下剤の内服で調整しましょう。
蒸れや暑さ、痒さによる不快感
オムツ着用による蒸れ、暑さ、搔痒感から便を弄びます。排便・排尿のリズムを見つけ、言葉やサインを見分けてトイレに誘導或いはオムツの定期交換をするのが良いでしょう。
生理的要因
トイレまで行こうとするが間に合わず、途中で失禁したり廊下の隅で放尿・放便してしまいます。汚したことを恥じて押し入れに汚れた衣類をしまい込んでしまうこともあります。排便・排尿のリズムやサインを見つけて定期的にトイレに誘導すると良いでしょう。身近にポータブルトイレを設置しても良いです。失禁等の際は叱責せず受容的な態度で接するようにしましょう。汚れた衣類を隠していた場合は羞恥心やプライドからそのような行為をするため、決して叱責せず本人がいないタイミングで処理するようにしましょう。
誤認や空間失認
トイレの場所が認識できなくて放尿・放便してしまいます。ポータブルトイレを見やすいところに設置しましょう。ポータブルトイレをトイレと認識できない場合は「便所」とわかりやすい標識を貼っても良いです。排便・排尿のリズムやサインを見つけて定期的にトイレに誘導しても良いです。
介護者の叱責やケアに対する反発
排泄の失敗を叱責されたり、羞恥心やプライドからかえって便を擦り付けたり隠したりします。介護者のケアに対して不満があり、その反発として弄便等の行為をすることもあります。介護者の接し方や対応に問題がなかったのか考える必要もあります。
退行現象
認知症が最重度になると便を不潔なものと認識できずに弄んだり、ゴミと思い込んで掴んだり、時には口へと運んでしまうこともあります。このような行為は赤ちゃん返りとも受け取れることから、誰からも関心が示されず、放置されてしまったときにおこることが多いようです。便を弄ぼうとしているときは、本人は便を他のものと思い込んでしまっている場合もあるため、何をしているところなのか問いかけます。そのことを受容したうえで、他のことに興味が移せるような誘導を行いましょう。
その他の周辺症状:攻撃的な言動への対応
認知症高齢者は感情のコントロールがうまくできず、怒り出すと酷い言葉で相手を非難したり、暴力をふるってきます。そのようなときは介護者が冷静になり、要因となっていることを調べてそれを取り除くことが必要です。命令や説得で抑え込もうとすると、かえって興奮させることになります。どうしても収まらない場合は介護者を代えたり、その場からいったん離れて危険がないかだけ見守るようにしましょう。このような言動が頻回になってきた場合は、薬剤治療が必要なこともあります。
状況の判断や理解ができないとき
話が理解できなかったり言葉やうまく伝えられずにイライラして怒り出すことがあります。少しの間、冷静に様子を見守るようにしましょう。しばらくすると何に腹を立てていたのかを忘れてしまい元の状態に戻ることがあります。
夜間覚醒したとき
夜間せん妄により夜間に覚醒すると、人が変わったように怒り出して暴力的になることがあります。混乱や危険がねければその場から離れて見守るようにしましょう。そのうち落ち着いてくるため、声の調子や表情が変わってきたことが確認できた際に声を掛けるようにします。
その他の周辺症状:性的言動への対応
認知症高齢者は自己抑制が十分に効かない場合があります。認知症の男性がケアをしている女性に対して、体に触れる等の行為をすることがあります。亡くなった妻と勘違いしていたり、元々好意を持っていたというケースも散見されます。いずれにしても寂しさや不安からこのような行為に及んでいることを理解する必要があります。自尊心を傷つけないよう、うまく相手の言動に対応します。強い口調や否定の態度は不安を招き、暴力的にさせてしまいます。寂しさのためのスキンシップを求めている場合もあるため、身体のマッサージや両手を握ってあげる等の対応をしても良さそうです。
まとめ
最後にこんなことを言ってしまうと元も子もなくなってしまいますが、はっきり言って非常に難しい問題・対応が求められると思います。特に同居しているご家族のストレスは多大なものでしょう。すべてを抱え込もうとせず、うまくサービスを利用しながら、お互いにちょうど良い落としどころを見つけるのが長く生活していくためのポイントのように思います。ご家族が心身ともに潰れてしまったらそれこそ元も子もなくなってしまいます。
一方、サービスを提供する側にとっても現実的にはなかなかしんどい問題だと思います。現場では常に少ない人数で対応を求められるためストレスを抱えてしまっている介護者も多いことでしょう。仕事とはいえ「感情的になるな」と言うは易く行うは難しです。とはいえやっぱり仕事なので、できるだけ冷静に判断する必要はあります。困ったことがあればすぐに相談しやすく、いつでも情報を共有できるような職場環境づくりが必要でしょう。
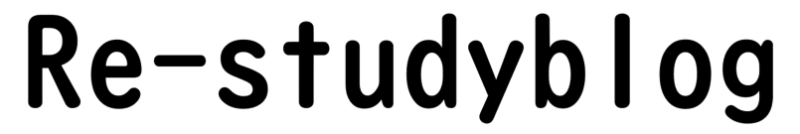


コメント