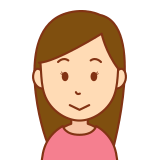
レビー小体型認知症の症状について教えてほしい。

レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に次いで多い変性性認知症疾患です。一般的にアルツハイマー型認知症よりも介護負担が大きく、生活上の課題を多く抱えています。今回はレビー小体型認知症の症状についてざっくりとまとめてみました。まずは症状を理解することが重要です。
レビー小体型認知症の全体像と症状
レビー小体型認知症(以下、DLB)はアルツハイマー型認知症(以下、AD)と同様、緩徐に進行するのが特徴です。認知機能障害については、ADの記憶障害と比べるとDLBの記憶障害はやや軽いものの、注意障害や遂行機能障害、特に視覚認知障害が強い傾向です。
DLBでは上記の認知機能障害に加え、認知機能の変動、誤認妄想、幻視、パーキンソン症候群、レム睡眠行動障害等が混在するのが特徴的であり実に様々な症状を呈します。それぞれの症状について説明していきます。
認知機能の変動
認知機能の変動は最も特徴的であり、DLBのおよそ84%に見られます。調子が良いときと悪いときの差が激しく、普段は普通にできていることが突然まったくできなくなったり、反応が乏しくなったり、会話が成り立たなくなるなどの症状が現れます。典型的な場合では数時間から数日、あるいは数週間から数ヵ月の経過で明らかな変動が見られます。
良いときには記憶力や反応もよく、日にちや時間、場所などのいわゆる見当識は普通に答えられます。しかし悪いときにはまったく話が通じず、周囲の環境なども理解できず、明らかにおかしい言動や行動が現れます。まるで別の世界で生活しているような、そんな違和感のある印象を感じます。なお認知機能の変動があるとき、誤認妄想が強くなるのもDLBの特徴と言えます。
幻視
幻視とは実際その場には存在しないにも関わらず、具体的であたかも目の前にいるかのように見える幻覚のことです。対象物の多くは虫や小動物、人です。DLBでは病初期から出現することが多く、「子どもが座敷で遊んでいる」「ご飯の上を虫が這っている」「壁やカーペットのシミや模様が虫に見える」等、ありありとした具体的な内容が特徴です。
幻視への対応は、本人が幻視を自覚していることもあるため、攻撃性や不安等を伴っていなければ「幻視があっても悪さをしないから大丈夫ですよ」と安心させ、見えていることを否定しないようにしましょう。
幻視と似たような症状ですが、視覚認知障害が日常生活に影響を及ぼすこともあります。例えばカーペット等の模様が落とし穴に見えて飛び越えようとしたり(錯視)、敷居が浮かび上がって見えて無理に跨ごうとしたり(錯視)、廊下が波打って見えてすくみ足が助長されたりします(変形視)。こういった場合はシンプルな生活環境にする等の対応が必要となります。
誤認妄想
誤認妄想とは誤った認識に基づく妄想のことで、例えば来てもいない人が来ている、よく知っている人物に別の人物が入れ替わっている、この家は自分の家ではない等といった内容です。DLBでは高頻度に認められることから、誤認妄想を認める場合はADよりもDLBを疑われます。
パーキンソン症候群(パーキンソニズム)
パーキンソン症候群(以下、パーキンソニズム)はDLBの25~50%に合併します。DLBのパーキンソニズムは動作緩慢や姿勢反射障害等の体幹症状が目立ち、左右差は少なく典型的な安静時振戦を伴わないことが多いです。
すくみ足症状については、純粋なパーキンソン病よりもDLBのほうが頻度が高く、その重症度も高くなっていたと報告されています。DLBでは、例えば歩行中に壁のポスター等が気になると、いったん停止して凝視することがあります。その後、歩行を再開しようとすると、すくみ足や姿勢反射障害のため転倒することもあります。このような場合、何に注意を向いたのか、その原因を探索して環境調整を行う必要があるかもしれません。
レム睡眠行動障害
睡眠には眠りが浅く夢を見やすいレム睡眠期、眠りが深く夢を見にくいノンレム睡眠期があります。通常、レム睡眠期では筋緊張が低下していますが、レム睡眠行動障害では筋緊張が低下せず、夢の内容がそのまま行動化されてしまうため、大きな寝言を言ったり叫んだり、或いは壁を殴ったり蹴飛ばしたりしてしまいます。このような場合はベッド周囲の環境調整や転倒・転落防止等の対策が必要になってくるでしょう。
レム睡眠行動障害にせよ夜間不眠にせよ、これら睡眠障害は認知症患者に高頻度でみられ、日中の各制度や身体活動性を低下させます。少なからず対応するならば、やはり日中の活動量を高めることが望ましいと思われます。
まとめ
臨床で実際にDLBの患者さんを診ていて思うことは、独特な認知症だなという感想です。上記した認知機能の変動、誤認妄想、幻視、パーキンソン症候群、レム睡眠行動障害はほぼ必発ですが、特に認知機能の変動には「つかみどころがない」というのが率直な印象であり、初見ではかなり戸惑います。比べるのも変な話ですが、ADの患者さんよりもとっつきにくい存在だと思います。
しかし「DLBはこういう症状なんだ」ということを理屈で理解できると見方がだいぶ変わってきます。それと同時に「なんてわかりやすいんだ」という感想すら覚えると思います。家族であれ医療介護職であれ、冷静に落ち着いて対応するためにもやはり症状の理解は必要だと思われます。そのためにもまずは正しい診断をしてもらうことが重要でしょう。
参考文献
博野信次:臨床認知症学入門 改定2版, 金芳堂, 2007
理学療法ジャーナル, Vo1. 54 No.2, 医学書院, 2020
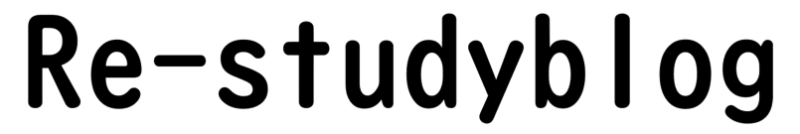



コメント